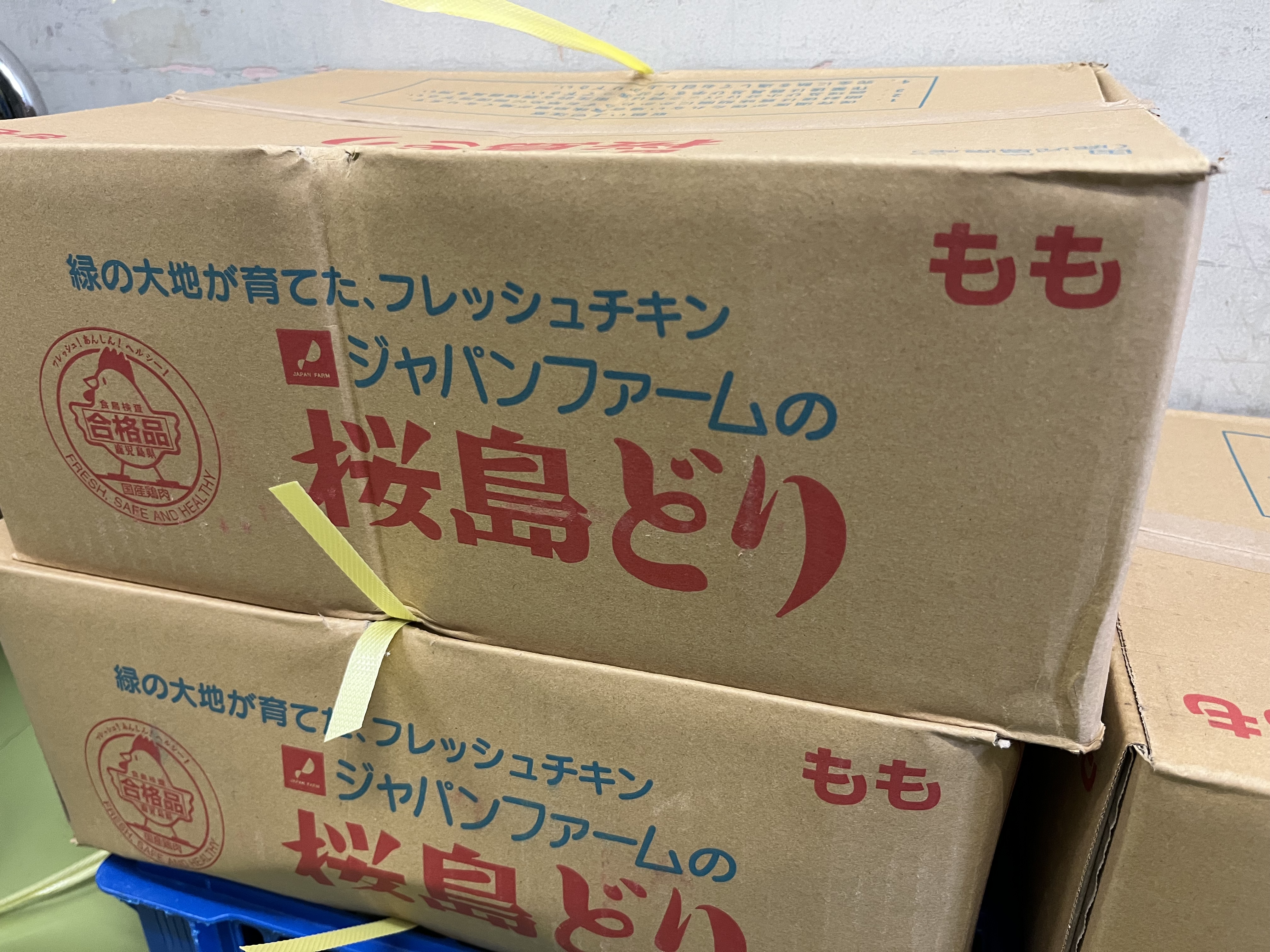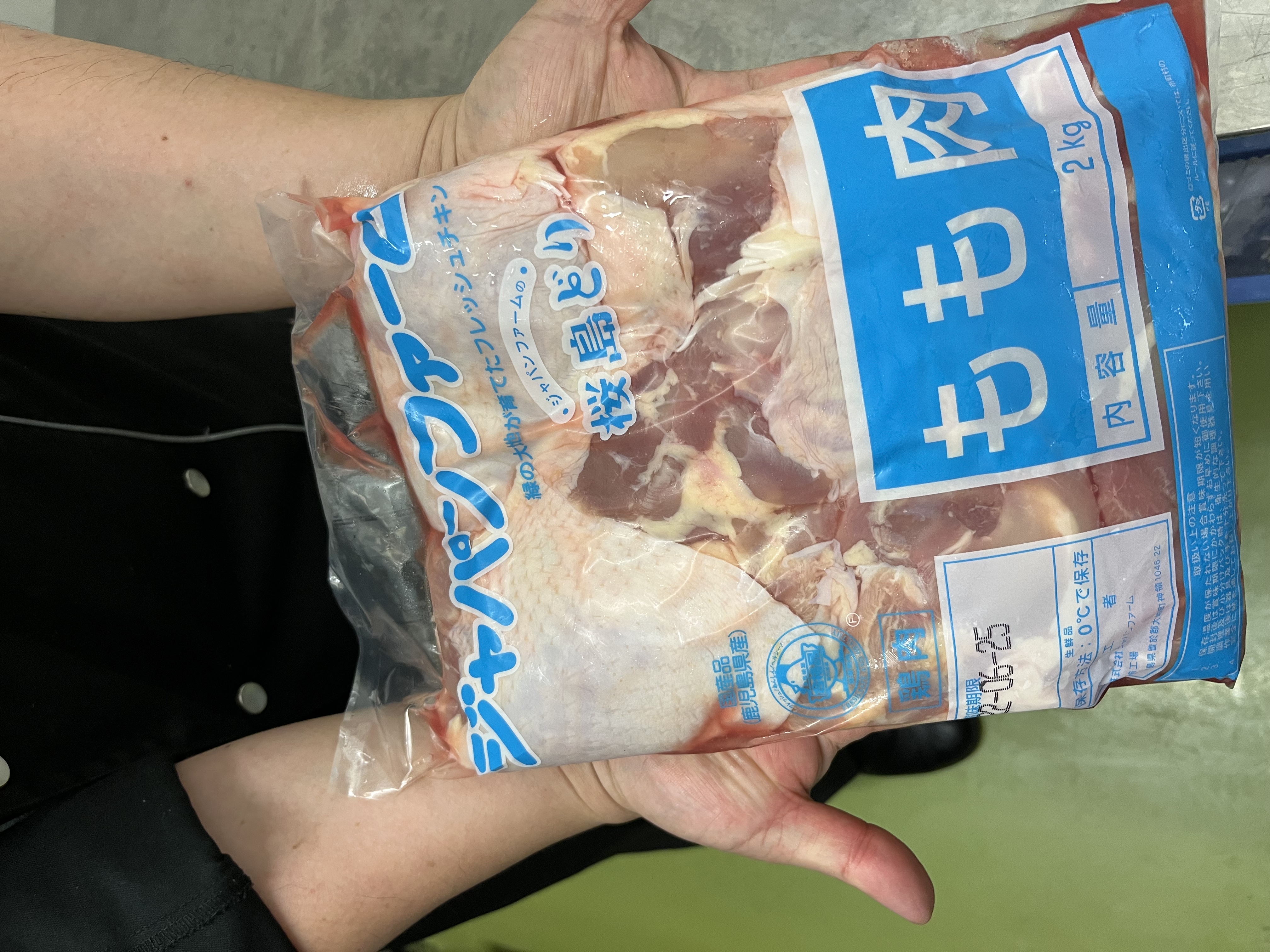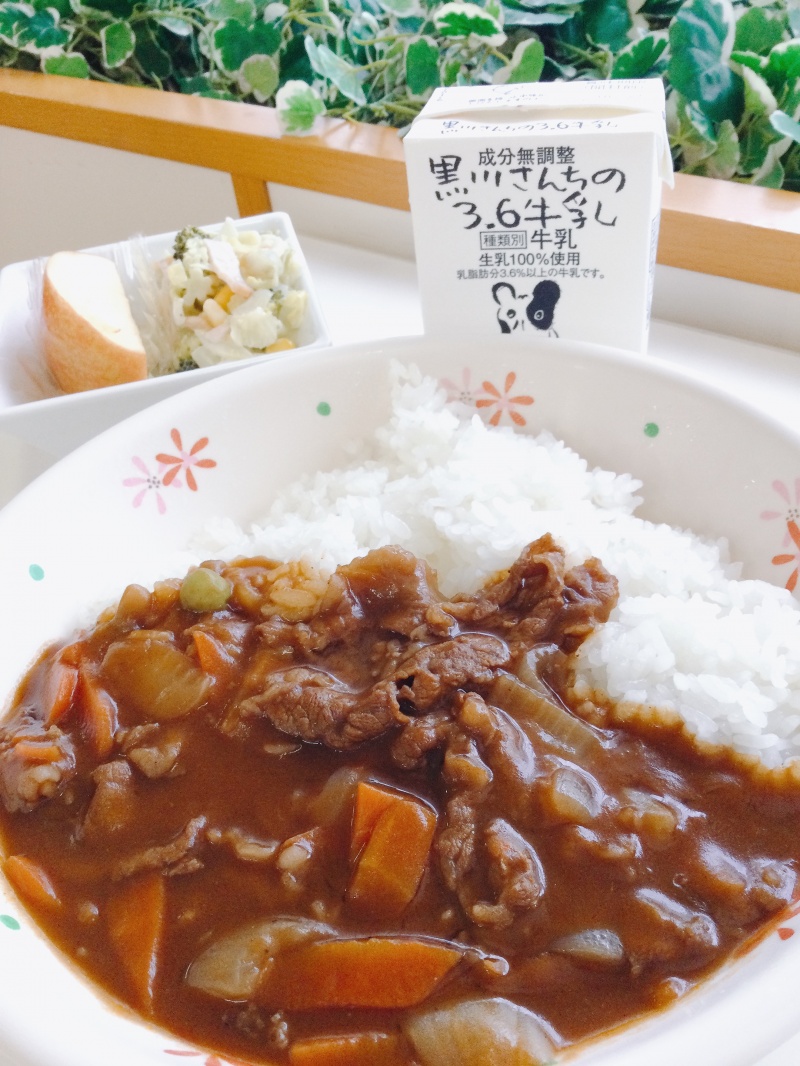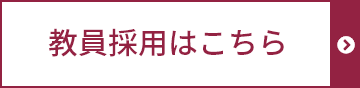スペシャル
和食
洋食
和食
洋食
カレイのトマトチーズ焼き
中華
スペシャル
郷土料理
和食
世界の料理